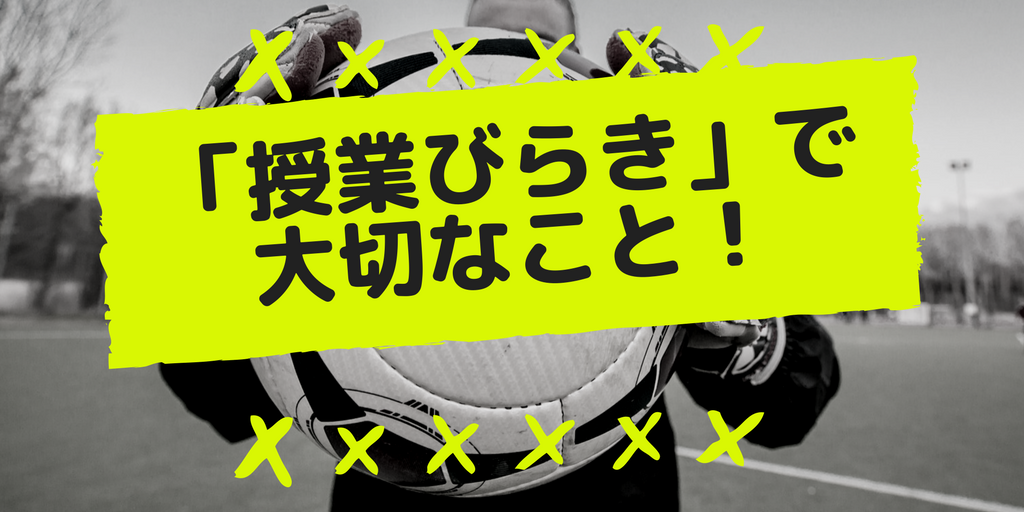
学級びらきや授業びらきの時期です。
色々とばたつく時期ですが、何事も最初が肝心。
今日は授業びらきについてまとめておきます。
授業びらきで最も重要なことは?
結論から言うと、
①なぜこの科目を学ぶのか(学習目的)
②なぜこのやり方で学ぶのか(学習方法)
③この授業を通してどうなることが期待されるか(変容)
の3点をはずしてはいけないだろうな、と感じています。
もちろん、一般的な授業びらきにおける初回ガイダンスとしては、
- 教員の自己紹介
- (アイスブレイクも兼ねた生徒同士の自己紹介・他己紹介)
- 授業内容
- 授業形態
- 授業スケジュール
- 授業の心構えやルール
- 成績評価の種類と方法
- 家庭学習の方法
のうちからいくつか必要なものを行うことになるでしょう。
さらにもう一歩踏みこんで、生徒の興味関心を引き付けるような授業内容に即した導入を行うこともあります。
私の場合は、最初に単元内容にちなんだ作品を読む活動をしたり、自分が考えたこと・考えになりそうな欠片をたくさん書く活動などをしています。ちょっとワクワクする要素も取り入れて、なんか面白そうかも、と思ってもらえるのも大事。ガイダンスとこれらの活動で半々くらいの設計にしています。また、Google classroom等を利用して使えるリソースをそちらに事前に載せておくこともしています。
まずは、こうした内容を組み合わせて、初回の授業時間をデザインすることから始めてみてはどうでしょう。
と同時に強調したいのは、やっぱり最初の3点の重要性です。
①なぜこの科目を学ぶのか(学習目的)
1年間生徒と授業を行っていると、必ずどこかで誰かが聞いてくる質問だと思います。
と言うか、高校生にもなれば、思っているけど、わざわざ聞かない。
「そういうもんだ」と、“大人”の処理をしてくれる。
教員はその大人の処理に甘えて、「やるときはやるんだ」とか「やってれば分かる」と言う言葉でお茶を濁しがちではないでしょうか?(一部では正しいんだけど)
そんな対応に、「そういう対応では、教育の効果は出にくい」と警鐘を鳴らしていたのが以前紹介したこちらの本。 少し引用すると、

教育の効果: メタ分析による学力に影響を与える要因の効果の可視化
- 作者: ジョンハッティ,John Hattie,山森光陽
- 出版社/メーカー: 図書文化社
- 発売日: 2018/02/20
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログ (1件) を見る
学習目標を持つよう促された学習者たちは、自分の知的能力について不安に思う傾向が低く、学習に集中して、効果的な問題解決方略の使用を継続した
※学習目的と学習目標は微妙に異なるところもある、と言うツッコミはあるけれど、学習目的を具体化したものの1つが学習目標だという定義
ここで引用した研究以外でも学習目標の設定は教育の「望ましい効果」を担保するものとして研究成果がまとめられています。
なぜ学ぶのか、どうしてこの内容を扱うのか、この分野の面白さはどこにあるのか、そんなことを授業で小出しにしていくことは多くの教員が行っているはず。
そんな風に、経験と流れで提示する学習目的も大事だと思うけれど(教科への情熱がある教員は学齢・学力問わず求められているし、それが教員の大前提)、
授業をデザインする視点に立てば、自分の言葉ではじめに明示する努力をして授業びらきに臨みたいですね。
②なぜこのやり方で学ぶのか(学習方法)
「学力の3要素」をつけるための学習方法がアクティブラーニングである。
という立場に立って授業を設計すれば、授業は当然、アクティブラーニング型になるだろう。(当たり前か)
だけど、生徒は「なぜそんなやり方をしなきゃいけないのか?」という疑問を持っている。間違いなく。聞いているだけで理解できるし、楽ならそれでいいじゃないかと。
でも、やっぱりそれでは不十分。
教員がせっかく勉強して実践した方法も、生徒がその意義を理解していなければ、勿体無い。
西川先生が「なぜ学びあいを行うのか」の説明をしっかり行ってこその「学びあい」だ、ということは再三指摘している通りです。
私も、昨年度末の生徒アンケートで
なんのためにやっているか分からず、先生の自己満足感が強い授業だった
と生徒が書いてくれたので、大いに反省して今年度は学習方略の意義説明もしたいと思います。
ここまで①と②の2点について説明してきましたが、
①と②の両者を規定するのが③、という意味で最後の③が最重要かもしれません。
③この授業を通してどうなることが期待されるか(変容)
『教育の効果』から引用(太字・下線は引用者)すると、
能動的な指導というのは多くの場合逆向きで計画されるものである。教科書ありきで指導を考えたり、好みの指導内容や、伝統的な学習活動から指導計画を構想したりするのではなく、期待する成果(達成目標と到達基準)から構想するという意味で逆向き設計と呼ぶ。
このように授業を計画することで、学習者に対しては明確な考え方の枠組みを持つこと、ひいては自分自身で自己調整的に知識や考え方を身につけることができるようになること、なぜ意図的に設定された練習に取り組む必要があるのか納得することを促す。
これで伝わるでしょうか?
「期待する成果」から授業を構想することの重要性が。
- どこへ向かうべきか
- どのように向かうべきか
- 次なる段階はどこか
への視点の重要性は『教育の効果』で再三語られていますが、
授業びらきで全てを説明せずとも、1年後の期待される成長像を提示することって、一つの重要な教員の役割じゃないかな、と感じます。
授業びらきに関する田尻先生のQ&Aのなかで、
先輩の中3の2、3学期の姿を映像で見せる。
という答えがあるのも、ある意味同じことをしているのではないでしょうか。
おわりに
①なぜこの科目を学ぶのか(学習目的)
②なぜこのやり方で学ぶのか(学習方法)
③この授業を通してどうなることが期待されるか(変容)
たかが初回、されど初回。教育が理想を失ったら終わりなので、初回の授業はある意味で理想を実現しやすい環境でもあります。ぜひそれぞれの先生が理想を込めた、でも肩ひじ張らない初回になるとよいですね。
色々な引用を加えたので、書評のようになってしまったけれど、
授業びらきのタイミングでこうした内容に触れておくことが、効果のある教育を実現する第一歩であると思っています。
最後にもう一度『教育の効果』から引用。
学習の個別化を図ること、学習者の到達度を正確に把握すること、そしていつ、どのように指導方法を変えたり、別の学習方略とはどのようなものなのかを教師が専門的に学ぶことこそが効果的なのである。
効果的な授業を目指して、今年度も努力したいと思います。
たくさん引用したので、よかったら書評記事もご覧ください。
