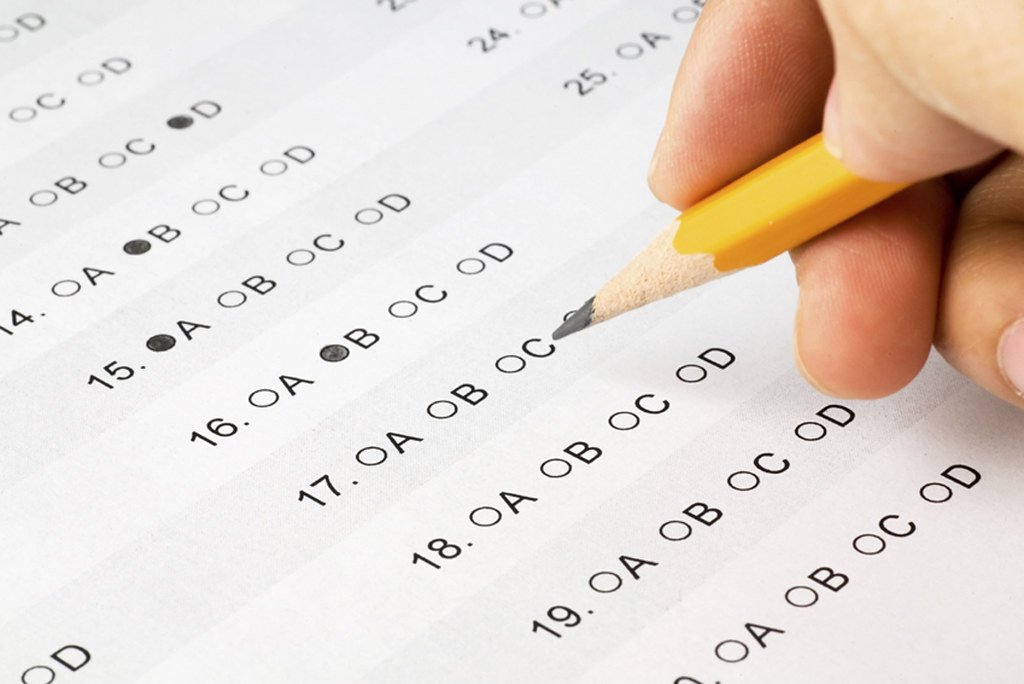12月の前半は、定期試験や成績処理等でまさに「師走」といった学校さんも多いと思います。教員としてはミスが許されない緊張感のある仕事ですね。
そんな教員目線をちょっとだけ公開します。教員の方だけではなく、お子さんがいらっしゃる保護者の方にも役立つかも?
①試験に出すことの約8割は授業前に決めている
これはこちらの本にも書かれていることです。
当たり前ですが、授業前に決めているから試験内容を反映した授業をします。だから、授業を大事にしてほしいのです。
(西川先生の本は拠って立つ理論・目的があり、誰でも可能な実践が公開されているため、とっても参考になるのですが、本ごとの棲み分けがイマイチなので何を読むか悩ましいです)

子どもが夢中になる課題づくり入門<会話形式でわかる『学び合い』テクニック> (THE教師力ハンドブック)
- 作者: 西川純
- 出版社/メーカー: 明治図書出版
- 発売日: 2015/02/20
- メディア: 単行本
- この商品を含むブログを見る
試験に出す内容は、授業前に決めろ、というもの。「目標と評価を決めてから、それを実現するための授業を考えるべき」であり、そのことを甘く考えている教員が多いと書かれています。
もちろん、経験によって感覚値でテストに出すことは分かっている教員が多いのですが、「そのために授業でこういう学習活動を行う」というところまで「毎回達成する」というと、難しいのかもしれませんね。(それが甘さなのだろうけど)
②「簡単・普通・難しい」の3レベルの問題を用意する
こちらにも、英文ですが「効果的な試験の実践方法」として書かれています。
当たり前といえば、当たり前ですが,これがないと正確な学力を反映できません。(学力とは何だ論争は一旦棚上げ) 簡単に言えば、教員はテストを作るとき必ず、「努力が報われるテスト」にしたいと思っています。
③できるだけ採点は楽にする
3レベルの問題を用意した上で、なるべく採点を楽にすることも大切な仕事です。というか、これこそ経験がモノを言うところだと私は思います。特に、
・回答欄のつくり方(つまり問題の並べ方)
・「難しい」問題を記号問題にする工夫
ですね。
初任のとき一緒に組ませて頂いた先生のテストを参考に作りましたが、自分のテストはまあ採点しにくかった(笑)回答欄ひとつとっても、採点しやすい工夫というのがあります。
多くの先生が、採点は生徒毎に行いません。問題毎に行います。であれば、採点しやすいレイアウトを考える。ということの大切さが今はよくわかります。
◯おわりに
前言撤回するようですが、上の3つはいずれも「答えが大方1つに定まっている問題」の話です。
これから中学・高校でどうなるか、を私なりに予測すると、
・知識の確認は日常の小テスト
・定期試験は持ち込み可で、がっつり書かせるテスト
・授業内の諸活動も数値評価
するなど、ハイブリッド型の評価が求められる時代になると思います。というか海外の大学では当たり前にそういう評価です。
「何が評価の何%となり、どう評価されるか」が明確です。学びの設計視点です。
先手を打ってみたいなあ・・・と思い、学年末の試験にぶちこめるか、画策中です。