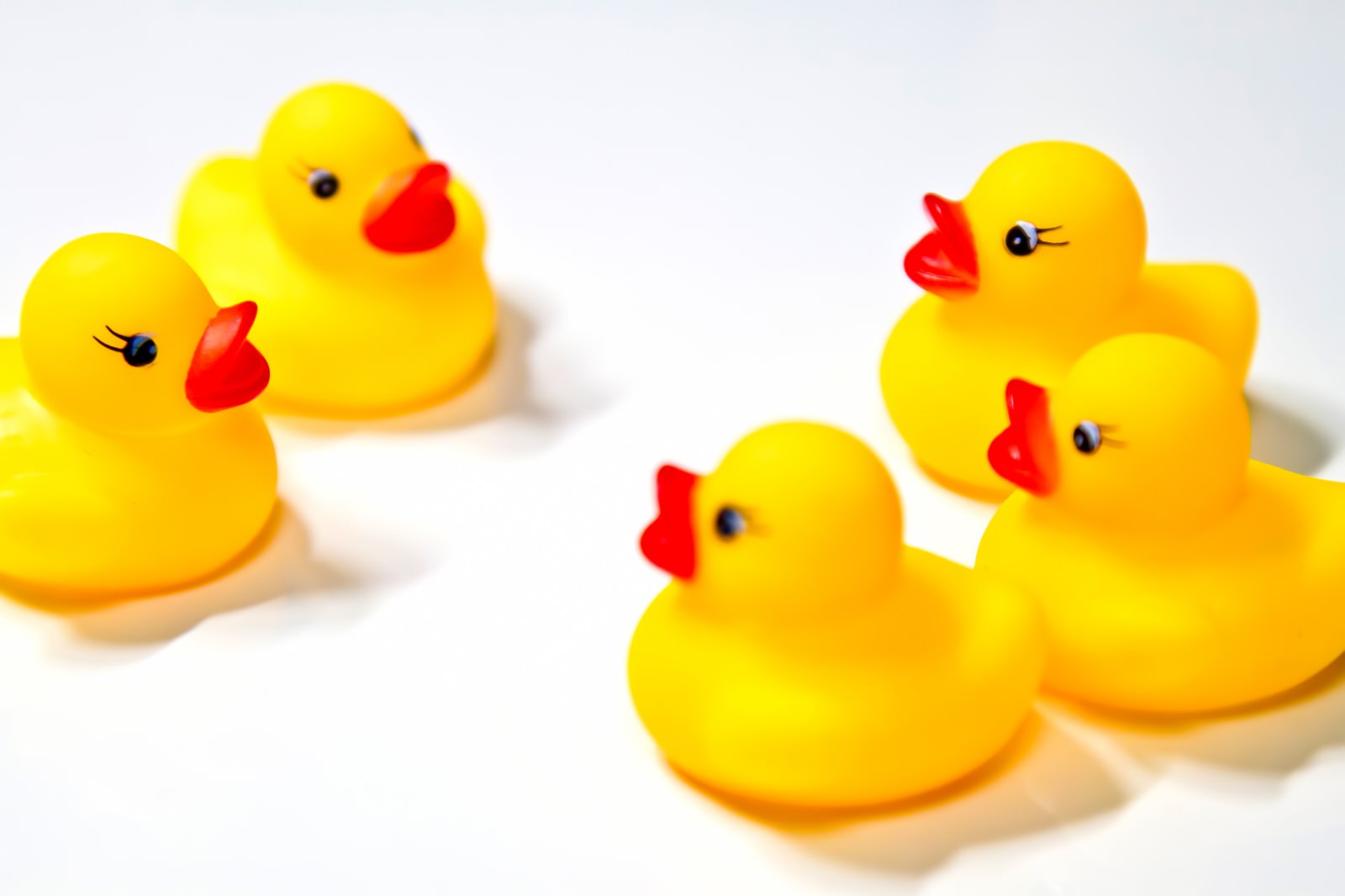
多数決以外の決め方をいくつあげられるだろうか?
くじ引きやじゃんけん?責任者での話し合い?学校現場での「決め方」はワンパターンだ。
しかし、いつから多数決が当たり前に使われるようになったのだろう?
クラスの委員決め、合唱曲の曲決め、指定校枠での推薦者決め、なんでもかんでも学校現場の意思決定は多数決だ。あるいは管理職の一存(小声)。
学校現場は生徒たちの意思決定を促す場でなければならない。
その意思決定が、意外と適当にやり過ごされている、と思わせてくれるのはこの本だ。
学級委員の決め方と米大統領の決め方の弱み?
学級委員も、大統領も、ほとんどの場合は選挙になるだろう。推薦で無投票当選なんてことはなかなか起きえない(高学年になると出来レース化してくることも否めないのだが)。
1つのクラスから2人選ぶ学級委員選挙も、
1つの国から1人だけ選ぶ大統領選挙も、
候補者が3人以上いる場合は同じ弱みを持っている。
それが「票の割れ」だ。
例)男子と女子が20人ずつの計40人クラス…
男子から2人立候補、女子から1人、学級委員の立候補が出たとしよう。
選ばれるのは3人の中から2人だ。
なんとなく想像がつく方が多いだろうが、大体男子1人、女子1人が選ばれるだろう。
なぜそういうことが起きるのか?
ずばり、票の割れだ。なぜか生徒の多くは、2人とも男子・女子(でもまったく構わないのだが)ではなく、男女1人ずつを選ぼうと思ってしまう。
したがって、男子も女子も、その立候補した女子があまりに的外れでなければ、
「その女子と、男子のどっちか」を選ぶのだ。
その結果、男子同士で票を奪い合う、ということが起こる。
もちろん、そんなことを誰も問題視はしない、のだが。
現実に起きていること
決してこれはたとえ話ではない。
2000年のアメリカ大統領選挙を例に挙げよう。当初の世論調査では、民主党のゴアが共和党のブッシュに勝っていた。だが途中で泡沫候補のラルフ・ネーダーが立候補を表明、最終的に支持層が重なるゴアの票を食い、ブッシュが漁夫の利を得て当選した。多数決は「票の割れ」にひどく弱いわけだ。」(坂井豊隆『多数決を疑う』)
こうして、現実的に票は割れていく。
国会議員の選挙でもそうだ。
2016年の参議院選挙でも、小選挙区で、自民党vs民進党vs幸福実現党の構図が生まれたとき、自民候補が民進候補に惜敗するケースがあった。

それは保守寄りといえる幸福実現党の候補が、政策のかぶる自民党候補の票を食い、それによって自民候補の票が伸びず、民進候補にその分だけ及ばなかったからだ。
逆に、自民vs民主vs共産の構図となり、民主と共産で票を食い合い、それが自民候補の当選につながったケースもある。(代表が敗れた、2014年の衆院選)

ただ一つ言えることは、私たちは決めているようで、決めさせられている。
なぜこんなことが起こるのか?
それは、多数決という決め方のルールが、「1位」しか表明できないルールだからだ。
多数決のもとで有権者は、自分の判断のうちごく一部にすぎない「どの候補者を一番に支持するか」しか表明できない。二番や三番への意思表明は一切できないわけだ。(坂井豊隆『多数決を疑う』)
順位をつけて投票する、となれば、「票の割れ」は防げるかもしれない。
もちろん、そうした選挙制度を国政レベルで整えるのは至難の業だ。
ただ、今の決め方は決して「総意」どころか「民意」を適切に反映しているものではない、ということは、頭に置いておきたい。
そうでないと、「悔しかったら選挙で勝て」みたいな発言をしてしまうことになる。
おわりに
とりあえずすべての学校教員はこれを読んで安易な多数決を控える教育をしたほうがいいんじゃないか。それこそがシティズンシップではないか。
シティズンシップはそういう、”生活”目線のもので、
教科として「教えられるべき知識」とは違って経験ベースの部分が強いものだと感じる。
新書よりも、こっちの方が読みやすいかも。
内容は結構かぶっている。ケーススタディが違うのと 、図が多め。あと地味だが巻末に「索引」があるのはありがたい。

「決め方」の経済学―――「みんなの意見のまとめ方」を科学する
- 作者: 坂井豊貴
- 出版社/メーカー: ダイヤモンド社
- 発売日: 2016/07/01
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログ (10件) を見る
何かを「皆の意思で」決めた。そういう言葉のもつ”危うさ”を、論理的に自覚したい、という思いが何となくあるあなた、ぜひご一読を。
